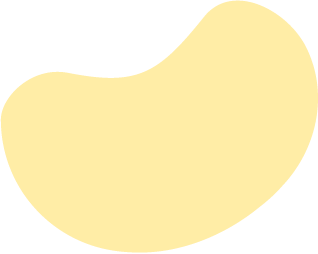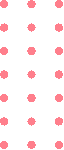2025年版!高校生の就学支援とは?
「子どもの教育無償化」という言葉がよく聞かれるようになり、「子どもの教育費は準備しなくてもよいのかも。」と思っている方もいらっしゃいます。ただ、子どもが複数いる場合の所得基準がわかりにくかったり、以前は対象にならなかったと思っていたら、改正があり対象になったなど、制度が頻繁に行われ、誤解の多い制度といえます。今回は、高校生の就学援助制度について整理してみます。


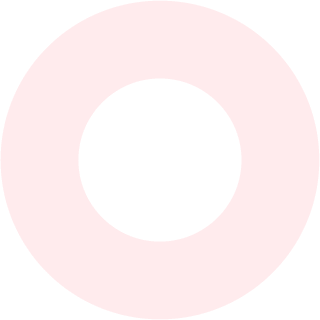
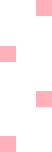

「子どもの教育無償化」という言葉がよく聞かれるようになり、「子どもの教育費は準備しなくてもよいのかも。」と思っている方もいらっしゃいます。ただ、子どもが複数いる場合の所得基準がわかりにくかったり、以前は対象にならなかったと思っていたら、改正があり対象になったなど、制度が頻繁に行われ、誤解の多い制度といえます。今回は、高校生の就学援助制度について整理してみます。

高校無償化、高等教育の就学支援新制度など、教育費を軽減するための制度は拡充傾向ですが、大学の授業料は年々増加しており、教育資金の負担に悩むご家庭も少なくありません。「コツコツ貯蓄」や「学資保険」「こども保険」などで準備する方法が一般的ですが、祖父母から教育資金の援助を受けるケースもよくあります。 ここでは、祖父母などからの支援を受ける際に、税制上のメリットがある「教育資金贈与非課税制度」について、概要やメリット、活用するときの注意点について解説します。
2025年2月。この時期の受験生は、本命と滑り止め校を受験するスケジュールを学校や塾の先生と相談して決定し、あとは健康に注意して当日を迎えるだけという状態でしょう。合格発表がされるまでは親子とも落ち着かない日々は続きますが、親ができること、そして、ぜひ、していただきたいことがあります。それは、受験生の時にかかった費用を振り返り、想定外の費用がどれほどかかったのかを見直すことです。今回は受験後の家計の見直しについてお話しします。
年末年始は、いつもよりも子どもにたくさんのお金が集まります。少子化が進んでいる昨今では、親や祖父母だけではなく、親の兄弟からの複数の財布を入れて「シックスポケット」という言い方をされることもあります。こんな時こそ、親子でお金の話ができるとき。子どもにとって、金銭感覚は一生ものの財産となります。ぜひ親子でお金について話してみましょう。
高校の進学費用は公立と私立で大きく異なります。私立に進学することになったら、公立といくら金額が違うのか。また総額でいくらとなるのか、不安に思う方もいらっしゃることでしょう。今回は「高校生にかかる教育費」について、公立と私立の違いと、具体的にかかる金額の把握方法について解説していきます。
文部科学省「令和6年度(速報)学校基本調査」によると、全国の中学校の生徒総数は3,141,166人。内訳は公立中学2,866,338人、国立中学26,846人、私立中学247,982人です。国立と私立を合わせると、約27.5万人にも上ります。全国でもっとも私立中学への進学率が高い地域は東京です。生徒総数313,943人に対し、私立中学の生徒数は82,697人(26.3%)と、すでに4人に1人を超えています。公立と私立では、かかる金額は大きく異なりますので、中学から私立に通わせるには、いくら必要なのか早めに把握しておくことがおすすめです。
人生における3大資金として「教育資金」「住宅資金」「老後資金」があります。「3大支出」とも言われており、これらがいくらかかるかを理解し、バランスよく、計画的に準備することで、将来に渡って安心できるライフプランが立てやすくなります。 ここでは、そのうちの2つである「教育資金」と「老後資金」の考え方について知り、バランスよく準備する方法について考えます。
1歳差きょうだいの年子、同じ日に生まれた双子。小さな2人が一緒に遊ぶ姿はとてもかわいいですよね。ただし、教育費の負担については、ほぼ同じタイミングで2人分が必要となりますから、早めに覚悟と準備をしておかなくてはなりません。今回は実際に双子を育てているFPが、年子や双子のきょうだい子供を育てるご両親に向けて、教育費の準備方法と注意点について解説します。
中学・高校の志望校を選ぶ際、偏差値や進学実績だけではなく、学校独自の魅力についても調べることでしょう。特色ある学校を見つける際のキーワードは、国際色豊か、探究活動、伝統校、起業家精神、サイエンス教育など様々です。今回は志望校選びの際によく目にする「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定校」について、その特徴と進学するメリットを解説します。