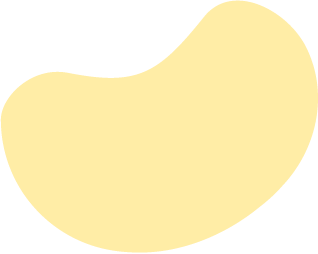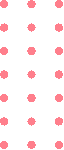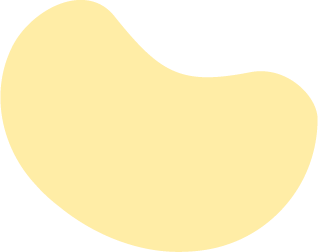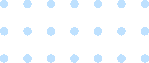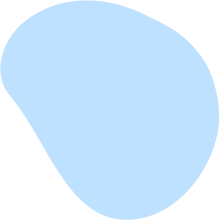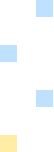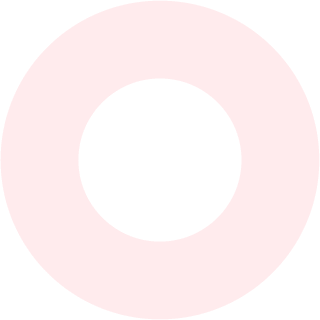
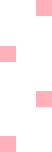
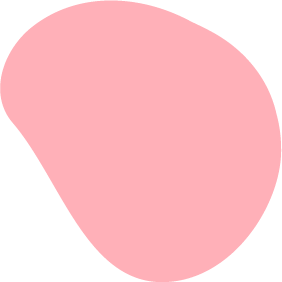
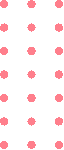
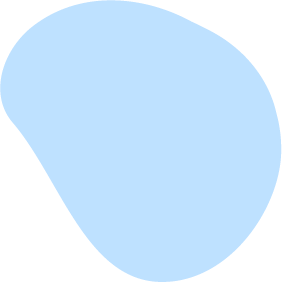
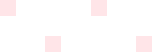
お子様の未来を支える 「祖父母からの教育資金贈与」とは?
高校無償化、高等教育の就学支援新制度など、教育費を軽減するための制度は拡充傾向ですが、大学の授業料は年々増加しており、教育資金の負担に悩むご家庭も少なくありません。「コツコツ貯蓄」や「学資保険」「こども保険」などで準備する方法が一般的ですが、祖父母から教育資金の援助を受けるケースもよくあります。
ここでは、祖父母などからの支援を受ける際に、税制上のメリットがある「教育資金贈与非課税制度」について、概要やメリット、活用するときの注意点について解説します。
教育資金贈与非課税制度とは
正式名称は「祖父母などからの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」です。30歳未満の受贈者(孫や子ども)が直系尊属(祖父母などの贈与者)から教育資金に充てるための贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば最大1,500万円までの贈与が非課税になります。(祖父母だけでなく、曽祖父母、父母等からの贈与が対象となりますが、叔父・叔母や兄弟からの贈与は対象外です。)
そもそも「贈与税」とは、人(贈与者)からお金をもらった際にかかる税金のことです。通常は、1年間(1月1日から12月31日)の贈与額が110万円を超えると、そのお金をもらった人(受贈者)は贈与税を払わなければなりません。しかし、祖父母などが孫や子どものために「教育資金」という明確な目的があって、一定の条件を満たしたうえで資金を贈与する場合は「1,500万円までは税金がかからないようにしてあげましょう!」ということです。
この「1,500万円」は受贈者(孫や子ども)1人当たりの非課税限度額であって、贈与者(祖父母などの贈与者)の限度額ではない点は注意が必要です。つまり、1人の子どもが、祖父母2人から1,000万円ずつ合計2,000万円を非課税で受け取ることはできません。一方、1人の祖父が、孫3人にそれぞれ1,000万円ずつ、合計3,000万円を贈与するのは問題ないということです。
この制度を活用すれば、贈与税を抑えつつ、高齢世代から若い世代へスムーズに資産の移転ができます。また、子どもにとっては教育資金を早期に確保できるというメリットがあります。
この制度は平成25年4月に導入され、令和5年3月までの事前措置でしたが、令和5年度の税制改正により3年間延長となり、令和8年の3月31日までの特例となっています。
教育資金一括贈与にかかる贈与税の非課税措置

出所: 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置:文部科学省
概要(教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置)
【参考サイト】
国税庁:祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|国税庁
0023004-114_02.pdf
教育資金贈与非課税制度の詳細
この制度を活用するためには、どのような資金が対象となり、どのような手続きが必要なのかを理解しておくことが大事です。ここでは、対象となる教育資金の範囲や、利用の流れについて解説します。
【対象となる教育資金】
制度の対象となる教育資金は、大きく分けて以下の2種類です。※1
①学校などに直接支払われるお金(非課税限度額:1,500万円)
・入学金、授業料、入園料、施設設備費又は入学、入園試験の検定料など
・学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など、学校等における教育に伴って必要な費用など
②学校等以外の教育に関する費用(非課税限度額:500万円)※2
・学習、ピアノ、絵画などの習い事、水泳や体操などのスポーツ教室や、教養の向上のための活動にかかる指導料
・指導のために使用する物品の購入費用など
・学校教育において、学校等必要と認めたものの購入費用
・通学定期代、留学のための渡航費などの交通費
・家庭教師の月謝や、TOEICや漢字検定などの検定料、通信教育
※1 23歳に達した受贈者については「学校などに支払われる費用」「学校等に関連する費用」「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用」に限ります。詳細は文部科学省のホームページでご確認ください。
文部科学省:教育資金Q&A(令和6年4月)
※2 学校以外の者に対して直接支払われるお金で、教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるもの。
手続き・利用の流れ
この制度を利用するためには、以下の手続きが必要です。【教育資金口座の開設と契約手続き】
①金融機関で、受贈者(孫や子ども)名義の「教育資金口座」の開設を行います。その際、贈与者と受贈者の続柄を証明する書類として、戸籍謄本や本人確認書類などが必要となります。贈与者は、口座を作る必要はないですが、受贈者との間で「贈与契約書」の作成と資金拠出の手続きが必要になります。
②契約した金融機関を通じて「教育資金非課税申告書」を提出します。
(申告書は,金融機関等の営業所等が受理した日に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされます。)
受贈者(孫や子ども)名義の信託口座を開設し、贈与者(祖父母など)より一括贈与(非課税拠出)します。
【教育費として使うときの手続き】
受贈者(孫や子ども)は、学校に支払う授業料や塾代など、支払った教育資金の領収書または請求書を金融機関に提出することで、信託口座から資金を引き出すことができます。
子どもが未成年の場合は、親などの保護者が代理で手続きすることができます。払い出し方法については、支払い年月日から1年以内など期限が決まっていますので、契約金融機関に確認するようにしましょう。
教育資金以外の目的で引き出すことは可能ですが、贈与税の対象となります。受贈者が30歳になるまでに使い切らなかった残額がある場合は、目的外払い出しの金額と合算して、教育資金口座の契約終了時に、税務署で手続きをして贈与税を支払うことになります。
教育資金贈与非課税制度を活用するメリット・デメリット
贈与者(祖父母など)と受贈者(孫や子ども)それぞれにメリットがあります。しかし、注意したいポイントもあるため、デメリットについても理解しておきましょう。【祖父母など(贈与者)にとってのメリット】
・祖父母などが孫や子に対して、まとまったお金を非課税で贈与することができる。
・資産が多い場合、相続税対策として活用できる。
・子ども名義の口座に「教育資金」目的で贈与するため、使い道が明確で安心感がある。
・複数の孫や子どもがいる場合に、公平にお金を分配することができる。
【孫や子ども(受贈者)にとってのメリット】
・祖父母などから税金(贈与税)を払うことなく、資金援助が受けられる。
・早い段階で教育資金を確保でき、不安が軽減され進学プランが立てやすくなる。
【祖父母など(贈与者)にとってのデメリット】
・金融機関で贈与契約や書類の作成、拠出など、手続きに手間がかかる。
・いったん贈与したお金は返してもらうことができない。
【孫や子ども(受贈者)にとってのデメリット】
・金融機関で口座を開設、贈与契約を結ぶなど、手続きに手間がかかる。
・教育資金以外の目的で払い出しがしにくい。
・払い出しの際、契約金融機関に領収書や書類の提出が必要。
・契約期間中に贈与者が死亡した場合「贈与者が死亡した旨」を契約金融機関に対して届け出る必要がある。また、管理残高が相続税の対象となる場合がある。(贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合など)
・30歳時点で残額がある場合、贈与税の申告が必要となる。
※ただし、30歳に達した日において学校等に在籍している場合などは、契約の継続が可能。
※受贈者が死亡した場合や、口座残高がゼロになり口座にかかる契約を終了させる合意があった場合は、契約は終了となる。
お子様の豊かな未来のために、制度を上手に活用しよう
「教育資金贈与非課税制度」は、孫や子どもの教育資金の支援をしたいと考えている方にとって有用な制度です。この制度を利用するには「贈与してくれる人」がいることが前提となりますが、仕組みを知っておくことで、将来的に教育資金の準備に困ったときなどに役立つことがあるかもしれません。実際、資産が多く相続税対策に悩まれていた方にこの制度を紹介したところ、「こんなすばらしい制度があるなんて知らなかった。大切な孫に『教育資金』に限定してお金をプレゼントできるなんて、本当にありがたい」と、すぐに制度を活用されたケースもあります。贈与する側、贈与してもらった側、双方にとってメリットのある制度といえます。
税制メリットを活かしながら、子どもの未来を支える1つの方法として、ぜひ、この制度を理解しておきましょう。
関連記事
教育資金は最優先?老後資金を踏まえてバランスよく
- ハッシュタグで関連記事を見てみる
- #スカラシップアドバイザー , #ファイナンシャルプランナー , #マネキャリサポーター , #合田菜実子 , #国家資格キャリアコンサルタント , #基礎心理カウンセラー , #教育費の準備 , #教育資金

- プロフィール : 合田 菜実子(ごうだ なみこ)
-
ファイナンシャルプランナー(CFP® 1級FP技能士) 国家資格キャリアコンサルタント 和光大学特任准教授 スカラシップアドバイザー(日本学生支援機構) 日本FP協会パーソナルファイナンスインストラクター 基礎心理カウンセラー
子育て期間中にファイナンシャルプランナー資格を取得。現在は、お金とキャリア教育の専門家(マネキャリサポーター®)として、若者たちの豊かな未来のために「金融経済教育」に積極的に取り組んでいる。金融庁関連、日本FP協会主催セミナーの他、大学や小中高校におけるお金の授業、高校での教育資金準備講座など講演多数。著書は『教えて合田先生!18歳までに知っておきたいお金の授業』(C&R研究所) 『子育て主婦が知っておきたいお金の話(経法ビジネス出版)』『小学生でもわかる、お金にまつわるそもそも事典』(C&R研究所 共著)など。
JFLEC (金融経済教育推進機構)認定アドバイザー
アドバイザー紹介ページ
日本FP協会パーソナルファイナンスインストラクター
https://www.jafp.or.jp/personal_finance/high/inst_disp/
和光大学特任准教授
https://www.wako.ac.jp/faculty-postgraduate/economics-business/economics/teacher.html
ウーマンライフパートナー会員 Women Life Partner
https://wlp.or.jp/
- オフィシャルWebサイト
- https://www.fpcareer.net/