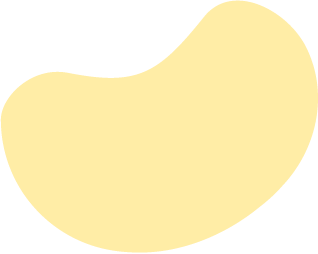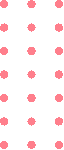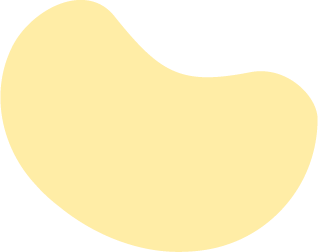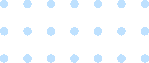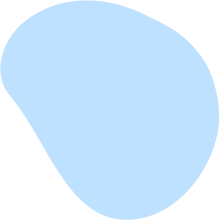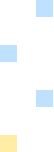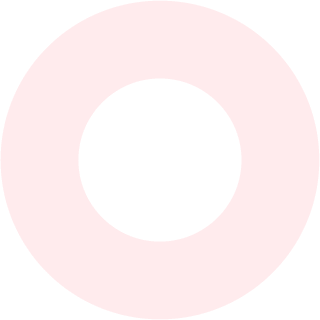
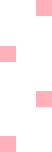
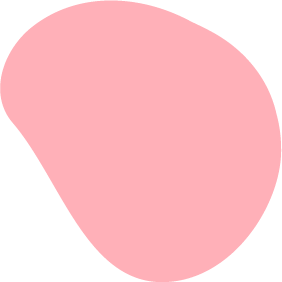
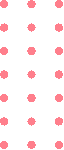
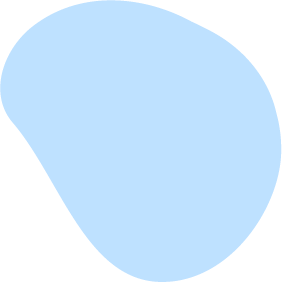
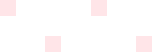
きょうだいがいるときの教育費。不足が無いか確認しておこう!
子どもの教育費、文部科学省の「子供の学習費調査(令和5年)」によると幼稚園3歳から高等学校3学年までの15年間の学習費総額がすべて公立であれば596万円、すべて私立であれば1,976万円となっています。これはあくまでも平均です。いくらきょうだいでも同じ進学ルートになるかどうかはわかりませんが、目安にはなります。今回は子どもが複数いる場合の教育費の準備について考えましょう。
文部科学省「令和5年度子供の学習費調査の結果を公表します」
教育費の考え方。「子どもが2人なら、2人目の教育費も1人目と同額を準備すればいい」というほど単純じゃない!?
最も子どもにかかる教育費が少なくなるのは、すべて「公立校」に進学する場合です。といっても、単純に、2人の子どもの教育費が596万円×2人=1,192万円となるわけではありません。また、複数の子どもが、全員同じ進学コースになるということもあまりないでしょう。さらに、いくら学校にかかる費用が安く済んでも、塾など学校以外にかかる費用には注意が必要です。中学受験のために小学生から通う子もいれば、高校受験をするために中学生から通う子どもなど、かかり始める時期は様々です。調査によると、学校以外の補助学習費については、私立よりも公立に進学した方が増加しているというデータも公開されています。いくら児童手当が18歳まで期間延長がされたり、就学援助という政策的な経済的支援などがあるといっても、支援された金額をその都度消費してしまえば、一番教育費がかかる時期に使うという効果的な使い方ができません。きょうだいの年齢差も重要ポイントとなります。きょうだいの年齢差が3歳違い、もしくは6歳違いとなれば、塾代や講習費用、受験料や滑り止め校の入学金などが同時にかかりますので、一気に教育費が増額となります。学費などの支援はあるものの、受験にかかる費用の支援はありません。令和5年度の私立大学の初年度学生納付金は約136万円ですから、子どもの受験の組み合わせが「私立中学受験と私立大学受験」や、「私立高校受験と私立大学受験」など、組み合わせによってかかる総額は異なってきます。子どもの受験料が家計の中から支出できなければ、教育ローンなどに頼らざるを得なくなります。つまり、子どもが複数いたとしても、基本の考え方は「教育費のピーク、受験時に備えること」ということです。
文部科学省「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金等 平均額(定員1人当たり)の調査結果について」
教育資金はどう準備する?
児童手当は3歳未満や子どもの数によって多少支給額は異なりますが、仮に、月15,000円が18歳まで支給されたときの単純合計は324万円となります。この全額を貯蓄しておくと、初年度費用もしくは受験時の費用はかなりカバーできるはずです。この金額を、家計の口座にまとめておいておき、食費や他の費用、例えば、上の子の受験の費用などに使ってしまうと、下の子の受験料が不足します。受験までに、児童手当を全額貯蓄していない場合、どうしようかと思っている方もいるかもしません。その時には、一度、今保有している口座を整理して、子どもごとの教育費口座に分けてみてください。そして、年ごとの進学予定と目標貯蓄金額を入れた計画表を作成してみましょう。その計画で必要なのは、「いつ子どもが受験するのか」、「どの時点で私立受験や専門学校等の一時的な支出が増えるのか」「留学や習い事、資格取得など、学校以外にかかる費用はいつかかるか」など、子どもそれぞれの「時期」を書いた計画表を作成してみましょう。特に受験が重なる時期など、教育費のピークが把握できれば、貯蓄の目安が計画的にできるでしょう。例えば、筆者が作成した下記のライフイベント表(家族構成:夫・妻・長男・次男)によると、長男が中学受験をするとき、兄弟の同時受験はありませんが、長男の受験後から、学費の負担が重くなっています。この重い負担に家計が耐えられるのか、表にすることで一目でわかるので、ぜひ作成してみてください。

この「ピーク時」を把握すると、逆算して貯めやすいといえます。上記はあくまでも例となりますが、かかる費用が予測できれば、「いつまでにいくら」準備したらいいのか、今後いつからいつまでこの金額が必要なのかがわかり、次から次へと支出しがちな子どもの費用を俯瞰的に理解できるでしょう。きょうだいの教育費でポイントとなるのは、バランスです。親からすると、子どもを公平に扱いたいかもしれませんが、まったく同じに貯め、まったく同じに使うのは困難です。どちらかにかけすぎることなく、教育費を分配することが、子どもが複数いるご家庭の教育費の考え方となるでしょう。

- プロフィール : 當舎 緑(とうしゃ みどり)
-
社会保険労務士。行政書士。CFP®
一男二女の母。阪神淡路大震災の経験から、法律やお金の大切さを実感し、開業後は、顧問先の会社の労働保険関係や社会保険関係の手続き、相談にのる傍ら、一般消費者向けのセミナーや執筆活動も精力的に行っている。得意テーマは、教育資金の準備方法、社会保険の仕組み、エンディングノートの作り方、これから始めるやさしい終活、成年後見の活用方法、銀行を介さない家族信託の仕組みなど。著書は、『3級FP過去問題集』(金融ブックス)『子どもにかけるお金の本』(主婦の友社)など。
子どもにかけるお金を考える会メンバー
http://childmoney.grupo.jp/
一般社団法人かながわFP生活相談センター理事
http://kanagawafpsoudan.jimdo.com/
J-FLEC認定アドバイザー
https://www.j-flec.go.jp/advisors/
ウーマンライフパートナー会員 Women Life Partner
https://wlp.or.jp/
- オフィシャルWebサイト
- http://tosha.grupo.jp/